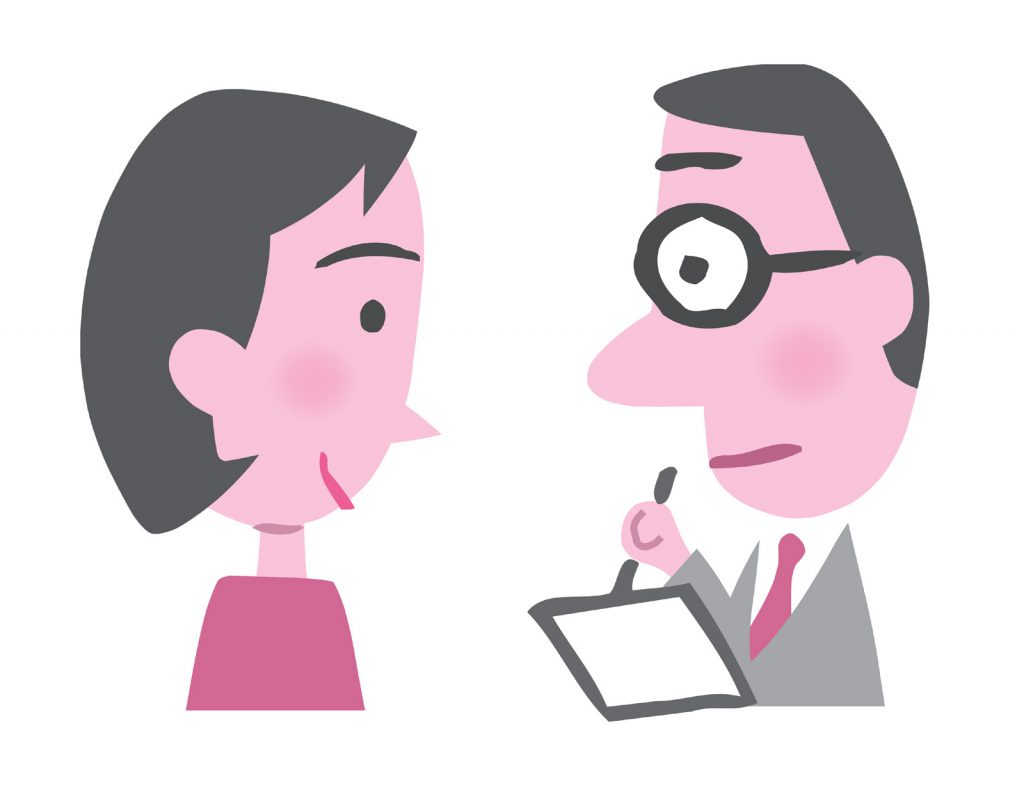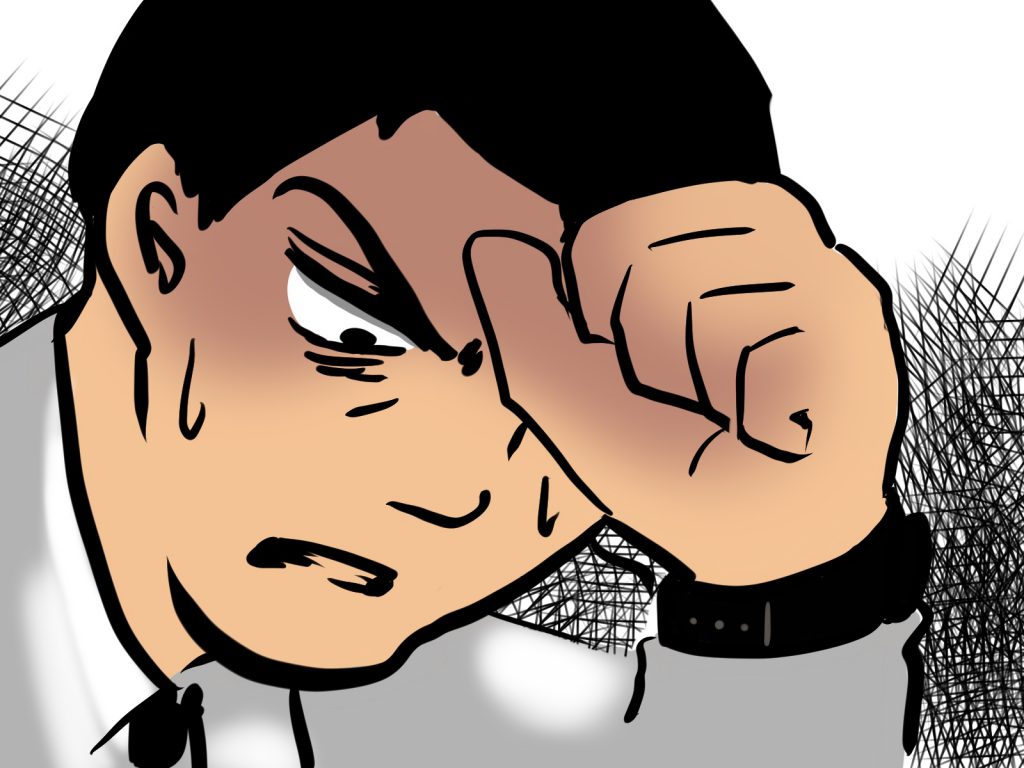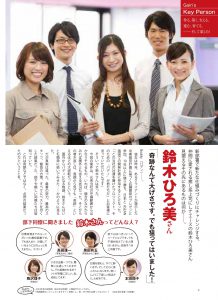ポッドキャスト社内報(社内ラジオ)の時代が来る!
採用よりも定着率とエンゲージメントが重視される時代
近年、多くの企業が従業員とのコミュニケーションを見直し、従業員エンゲージメントを高めるための新しい方法を模索しています。その中で注目を集めているのが、ポッドキャスト社内報(社内ラジオ)です。こうしたインナーコミュニケーションの手法がどんどん進化し、企業によってその手法が多様化するのは自然な話です。
その大きな理由が採用の厳しい環境にあると思われます。ゆえに、人が辞めない会社こそが業績アップの第一義。つまり定着率がこれまで以上に事業活動の生命線になってきています。インナーコミュニケーションや風土醸成にお金とパワーをかけるのは当たり前の話なのです。
このポッドキャスト社内報、なんといっても特性は、端末さえあればいつでもアクセスできるという利便性。ラジオというメディアの特性上、周知さえ行き届けば紙やウェブ社内報よりも、圧倒的な視聴率、閲覧率を誇ります。コンテンツも比較的、柔らかいコンテンツになるので、機能させることができればかなり有用なメディアになります。
そしてこれは、かなり業種を選びます。一つのスペースで机を並べて仕事をする、あるいは製造業のように常にきまった人がいる。そうした人がまとまっている業種には意外と向いていないかもしれません。
逆に、トラックやタクシーのドライバー、引っ越し業者、広い地域を一人の営業マンが担当するような営業主軸の会社、さらには単独で派遣されることの多いSEなど、自宅作業員が多いなど、比較的孤独でな個人にメッセージを伝えるのに最適なメディアとなります。
また、肉声を直接届けられるので、「読む」「見る」という行為よりも気楽でタスク感なく視聴者もアクセスする特性があります。活字には表せない、雰囲気、温かさなどを伝えられる点もユニーク。これは、じつはかなり大きな課題解決能力を含んでいることの証左です。
ポッドキャスト社内報(社内ラジオ)は、気軽なコストとパワーで、従業員とのつながりを強化し、信頼関係を深めることができます。理念や仕事に役立つ細やかなテクニックなども伝えられます。本記事では、この「社内ラジオ」の価値、導入による効果、そして私たちが提供する新サービスについて、丁寧にご説明します。
ポッドキャストが持つ価値とは?
ポッドキャストの最大の特徴は、「声」を通じて情報を発信できる点です。音声には、文章では伝わりにくい感情や思いが込められており、単なる情報共有を超えたメッセージの深みを生み出します。この特性は、特に以下のような場面で大きな効果を発揮します。
- リアルな声で、力強いメッセージを届ける
ポッドキャストを通じて、経営陣やリーダーが直接従業員に語りかけることで、理念やビジョンがより深く伝わります。特に企業の方向性や今後の展望を共有する場面では、「声」によるコミュニケーションが、従業員の理解と共感を高めます。また、声には文字以上の説得力があり、リスナーに感情的なつながりをもたらします。
- 個人で過ごす時間の多い従業員にも届く
トラックドライバー、タクシー運転手、引っ越し作業員、また単独で派遣されることの多いSE(システムエンジニア)など、日常的に個人で作業することが多い業界では、ポッドキャストは特に有効です。移動中や作業の合間に気軽に聞けるため、社内ラジオを通じた情報共有やモチベーションの維持が容易に実現できます。
- 採用支援メディアとしての活用
ポッドキャストを外部にも公開することで、求職者に企業の「素の顔」を伝えることが可能になります。人事部が作る広告や形式ばったメッセージとは異なり、経営陣や社員の声を通じて、企業の理念や雰囲気、働き方などを生き生きと伝えることができます。これにより、会社の透明性を示し、候補者に親しみを持たせることができます。
社内ラジオがもたらす効果
社内ラジオは、単なる情報発信ツールではありません。適切に活用することで、さまざまな効果を得ることができます。
- 企業理念やビジョンの浸透
定番の効果です。経営陣や部門長が定期的にメッセージを発信することで、企業全体としての方向性を従業員に共有できます。ただ伝わり方がカジュアルになり、ウェブや紙の活字メディアよりもフランクに伝わります。これにより、会社全体の一体感が醸成され、個々の従業員が企業理念をより深く理解することが可能になります。
- 部門間の情報共有を促進
ポッドキャストは、複数の部門や拠点を持つ企業にとって特に有用です。各部門の取り組みや成功事例を音声で共有することで、互いの理解を深め、部門間の連携を強化できます。また、お客様の評判を得た、喜ばれたといった事例を、より具体的に直接語り掛けるように伝えられます。情報の深度がある内容となり、これはウェブや紙にはまねができないものです。
- 従業員エンゲージメントの向上
ポッドキャストを活用すれば、従業員が「会社に必要とされている」と感じるきっかけを作ることができます。リーダーや同僚の声を直接聞くことで、会社への帰属意識が高まり、モチベーションの向上にもつながります。またそういう目的のプログラムを作ることが極めて容易という点も挙げられます。人が語るだけ、シンプルで最も強いメッセージなのです。
- 離れて働く従業員とのつながりを強化
リモートワークや現場勤務が多い企業では、従業員同士が直接顔を合わせる機会が減少しがちです。社内ラジオは、物理的な距離を超えて従業員同士や経営陣とのつながりを感じられる貴重な手段となります。
新サービスのモニタープランについて
現在、私たちはこの新しい「社内ラジオ」サービスのモニター企業を募集しています。モニター企業には、以下のサービスを無料でご提供いたします。
- 月4本の編集済み音声データを納品
1本あたり10~15分程度のポッドキャストを制作し、プロフェッショナルな編集を施して納品いたします。 - 通常料金13万円相当のサービスが無料
通常は月13万円でご提供しているサービスを、モニター期間中は無料でお試しいただけます。 - 配信サポートも含むトータルサービス
音声コンテンツの制作だけでなく、配信方法のサポートも行います。初めての企業でも安心して導入いただけます。
まとめ:社内ラジオで新しいコミュニケーションを実現
社内ラジオは、単なる情報伝達を超え、企業と従業員の信頼関係を築くためのツールとして大きな可能性を秘めています。特に、従業員が物理的に離れて働く機会が多い現代において、声を通じたコミュニケーションは、距離を超えた絆を生み出す力を持っています。
ぜひこの機会に、私たちの「社内ラジオ」サービスをお試しください。新しい形の社内コミュニケーションを体感し、企業の成長に役立てていただければ幸いです。
ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!